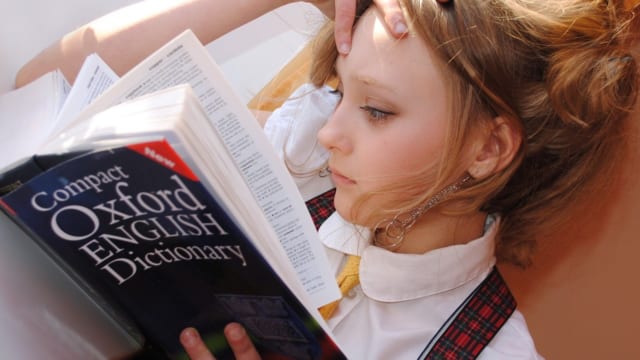日頃からいろんなジャンルの本を読むようにしているのですが、たまにとにかく分量が多く、文体も固く読むのが大変な本を読みたくなることがあります。こういう本は、日本の著者の書いた新書などと違って、漫然と読み進めても右から左に頭から抜けていくことが多いです。
そうならないために私がしている工夫を紹介します。
著者についての情報を集める
最初にすべきは著者がどんな人なのか、過去の著書などもあればどんな本を書いている人なのかを把握することです。これは本に限らず、あらゆるメディアの情報に言えることですが、世の中に主観が入っていない情報など存在しません。
どんなに公平中立、客観的で書くことに注力して書かれた本だったとしても、そこには必ずその著者独自の視点が入っているはずです。そしてそれを掴むためには、著者のバックグラウンドを知ることが早道です。
この著者がこういう経歴だから、こういう視点が持てるんだなということが分かれば、難しい本の理解も進むはずです。
本の要約を先に読む
翻訳書などに多いのですが、1つ1つのテーマについて、細かいエピソードが多く書かれていて、時間をかけて読んでいるうちにそもそも何の話題だったのか忘れてしまうということがあります。
ですが、本に何が書いてあるかをある程度知っていれば本筋からずれにくくなります。
有名な本であれば、書評ブロガーさんやYouTuberさんが本を紹介していることが多いので、ネットで検索すればすぐに出てくるでしょう。マンガでわかる○○のような本出ている場合、先にそちらを読んでから原書を読むというのもいいでしょう。
ビジネス書などの実用書の場合、ネタバレして困るということはないので。
その他、有料サービスですが本の要約をプロのライターさんが書いているflierなんかもおすすめです。
人に話す。ブログなどに書く
さて、事前準備も十分した上で本を読んで、なんとか頑張って本を読み切りました。ですが、実際に中身を振り返ってみると全然頭に残っていないということが結構多いのではないでしょうか(私だけかな)。
自分が本当にその本を理解出来たかどうか、理解度を測るためにはアウトプットをしてみると一目瞭然です。私のようにブログを書いている人ならば、ブログに書くのが一番ですが、そうでないなら人に本の内容を説明してみるだけでも、十分自分の理解度を把握出来ます。
無理して読まなくてもいい
ここまで書いて身も蓋もない話なのですが、私はその時に頭に入らないのであれば無理してその時に読む必要なないと考えています。多分、頭に入らないなら読むタイミングではないということだと考えています。
人の興味の対象なんて、どんどん変わっていくもの。今、そこまで興味が持てなくて頭に入らなかったとしても、1年後に読んだらスッと読み進められるかもしれません。
私は本は楽しんで読む。それが一番大事なことだと考えています。
今日のアクション
せっかく時間をかけて読んだ本は自分のモノにしたいです。読書にも事前準備が大切です。